 |
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
 |
 |
|
この世界の入って2年チョイ。まあよくも此れだけの車輌を買ったものだ(呆)。
僕が走らせる時間は19:00過ぎ。 部屋の中は其れ成りに暗い。 そのシチュエーションで、室内灯を点灯させた列車の美しさと言ったら・・・・・。 で、当初(2年前)に悩んだのは室内灯のちらつき。 要は、電力供給がキッチリと出来ていない。 まあ、電気屋の感覚では極普通な、M車(モーター内蔵)はまずチラつかない。 そうなんです。モーターは其れ成りの電流が流れますので、少々の接触不良は電流の多さで押し切ってしまう。 問題は微弱電流のLED。 僅かの接触不良でも電力供給が不安定に。 2年少々の経験ですが、この接触不良の原因は90%以上此処だな。と言う感触を得ました。 あ、この対処法はKATOの場合です(殆どの車両がKATOですので)。 まず、メーカーの設計不良。 室内灯の足と、車体側の金属の幅が合っていない。 車体側が広いんですね。 対策は室内灯の足を外側に広げて差し込む(僕の経験では全車両です)。 ネットでは此処を半田付け。なんてのも見受けますが止めましょう。室内灯の足を広げるだけで大丈夫です。 で、確認。室内灯の足が車体側の金属の正しい側に入っているか? 差込方が悪いと金属の裏側に入ります。 で、一番多い原因。 台車の集電板のくぼみに車輪シャフト先端が入ります。結構グラグラ状態ですよね。 このクリアランスタップリの状態で電流を流さないといけないんです。 つまり、この隙間にグリスが入ったら完全にNG。 メーカー出荷時にグリスが入っていますので、確実に排除。 変わりに潤滑作用のある(グリスの代わり)接点潤滑剤をほんのチョイ塗る。 まあ、導電板はブロンズと思われますので、潤滑不足でかじる恐れはまず有りません(無潤滑でも平気)。 つまり、このピボット部分の接触不良が、室内灯のチラツキの原因の殆どです。 チラついた車輌のこの部分のメンテで略100%治ります。 実は数日前、チラツキの解消にと暫くぶりにチラツキの目立つ箇所のレールを掃除。 全く関係なし。 面倒ですけど台車を分解、接点の掃除。 判っているんだから、サッサとやれよ。と言う結論でした。 PR |
 |
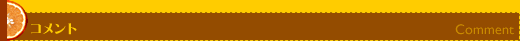 |
 |
|
|
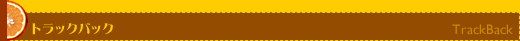 |
|
トラックバックURL |
|
忍者ブログ |





