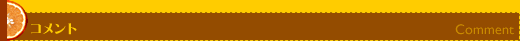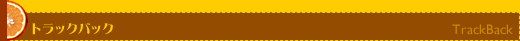兎に角悩んだ室内灯のちらつき。あの状態なら付けない方がよっぽどまし。
でも、きちっと点いた列車を見たら、元には戻れない。
そんな訳で、ちらつきの原因を見つけ対処をしようと言う事です。
処方が効いて安芸は10両全てのちらつきがゼロに成りました。
そう成ると柳の下の鰌を狙います。
安芸を片付けてカモメを出す(機関車の交代は無し、笑)。列車の走行を楽しむのではなくて室内灯がちらつく車両を見つけ対処をするのが目的です。
軽い対処はして有るカモメ。1両だけほんの僅かにちらつく。
全車両の対処をしたら結構な時間が掛かるので、ちらつきが発生した車両だけに対処します。

今回は床下もバラして、左右に付いている前後に延びた導電板もクラモリン処理。
初めて床下をばらしました。導電板の薄さには驚き。
この薄い導電板の前後の淵に近い所へ台車から出ている端子が接触します。
薄い導電板のスプリング効果に頼っている接点ですけど、この薄さではスプリングの強さが可也弱すぎると思います。つまり汚れ(酸化皮膜)を押し切るだけの力が足りないのです。
また、新しい課題を見つけてしまいました。

LEDの導電板は例の様に折り曲げ加工(加工した1両、とても好調です)。

今まで弄くって来て感じたのは、ちらつきの原因の一番の犯人は此処。
台車の集電板中央の突起部分。
此処の接触不良が原因でのちらつきを感じます。
この部分の接点の接触圧力が低過ぎるんですね。高いと台車の回転が重くなって脱線の原因にも成りますので難しい所です。
本来なら柔らかい配線材を使ってハンダ付け。と言うのが一番と思いますが・・・・。
導電板とLEDの足との間の接触不良は、LEDの足を本来の位置に差し込めば大丈夫と思います。此処の接点圧力はかなり高いですから。
あ、酔った勢いですので気にしないで下さい。
コンデンサーの追加等の処方、判りますけど僕は嫌いです。
対症療法なんですね。基本的に拙い所を治さないで逃げている。
職人ですので・・・(笑)。
更にデジタルコントロールを始めたらコンデンサーの追加はもう無理と思っています。
基本に戻って臭い物は元から絶たなきゃダメ、の精神です。
 [1回]
[1回]
PR